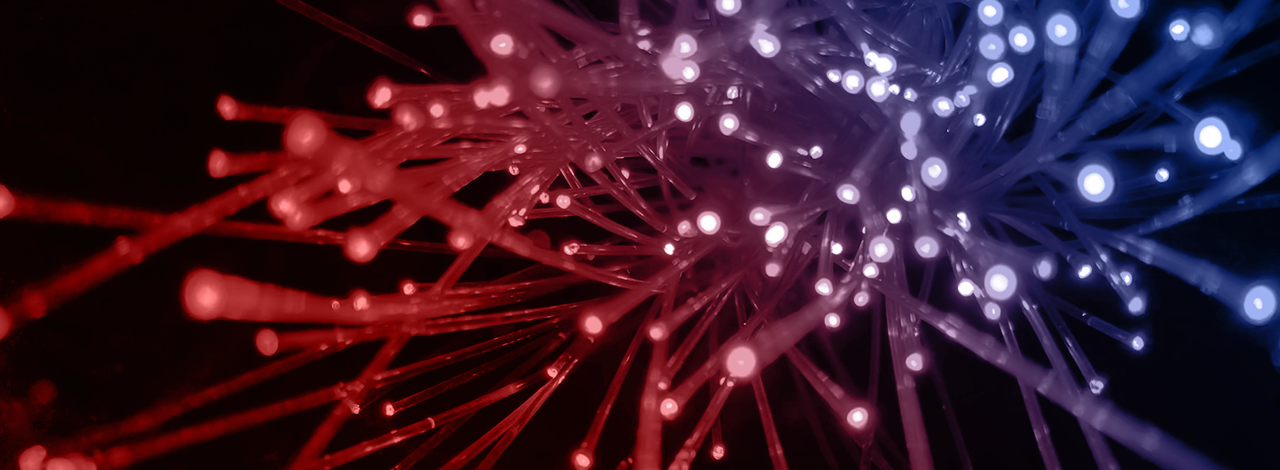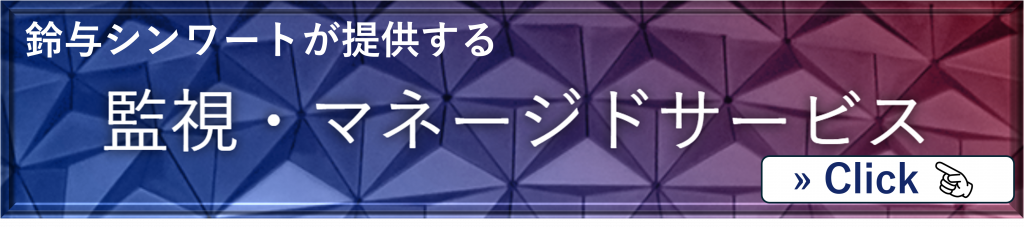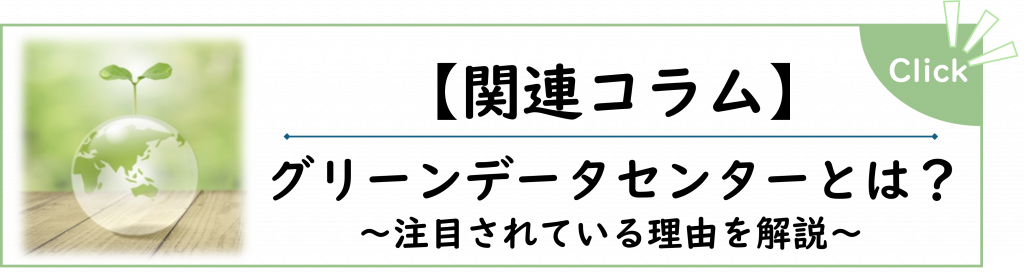地方分散型データセンターの可能性 ~選定のポイントについても解説~ 第15回 25年11月 / 最終更新:2025.11.20
目次
データセンターは、大量のデータを安全かつ効率的に処理する拠点として、今や社会インフラ(通信インフラ)の一部になっているといっても過言ではありません。また、クラウドサービスの拡大やAI・IoTの普及に伴うデータセンター需要の高まりに伴い、データセンターの建設ラッシュも続いています。
このような状況の中、近年では地方都市に拠点を置く「地方分散型データセンター」が注目を集めています。地方分散型データセンターは、リスク分散や再生可能エネルギーの活用、地域経済の活性化などさまざまな可能性を秘めています。
本コラムでは、地方分散型データセンターが注目される理由を整理し、都市型データセンターとの比較や選定のポイントについて解説します。
地方分散型データセンターが注目される理由
地方分散型データセンターとは、都市中心部から離れた地方都市などへ分散してデータセンターを配置する手法です。ここでは、地方分散型データセンターが注目される理由について解説します。
災害リスクを分散できる
地方分散型のデータセンターは、複数の地域に拠点を設置することで災害などのリスクを分散できるため、事業継続計画(BCP)の観点でも注目されています。
たとえば、都市部のデータセンターに加えて、地方都市にデータセンターをバックアップサイトとして配置することで、万一の障害発生時にもシステムを早期に復旧できる可能性が高くなります。このように、地震や大規模災害によって影響を受けたシステムやデータを迅速に復旧するための仕組みを、ディザスタ・リカバリ(DR)といいます。
再生可能エネルギーを活用しやすい
地方都市のデータセンターは、土地や送電網に余裕があり、風力や太陽光、水力といった再生可能エネルギーを活用しやすいなどの特徴があります。
以前のコラムでも解説した通り、データセンターの電力消費が環境に与える影響は大きな問題になっています。そのため、カーボンニュートラルの観点からも、再生可能エネルギーを積極的に活用できる地方型データセンターは大きな注目を集めています。
地域経済の活性化につながる
地方都市のデータセンターは、地域経済を活性化する効果も期待されています。
データセンターの建設や運用は、新たな雇用を創出し、地域産業の活性化と経済成長の促進につながります。自治体によってはデータセンターの誘致に積極的に取り組み、税制優遇や土地提供などの支援策を打ち出しているケースもあります。
都市型データセンターとの比較
データセンターは従来、東京や大阪といった都市中心部に集中する傾向がありました。しかし、災害時のリスクや電力供給逼迫の問題から、地方都市へ拠点を移すデータセンターが増加しています。
都市部のデータセンターと、地方都市のデータセンターではニーズや特徴も異なってきます。ここでは、都市型データセンターと地方型データセンターの違いについて解説します。
アクセス性とネットワーク遅延
都市型データセンターの最大の強みは、主要なユーザー企業やネットワーク接続拠点とのアクセス性が高いことです。物理的な距離が近いことで、ネットワーク遅延を最小限に留めることができるため、金融取引やリアルタイム処理が必要な分野へのニーズが高くなります。
一方、地方型データセンターはユーザー企業のネットワーク接続拠点との物理的距離によるネットワーク遅延などが課題となります。しかし、近年ではエッジコンピューティングの導入により、一定の処理をユーザーの近く対応することでネットワーク遅延を低減する取り組みが進んでいます。
コスト面
都市部では土地価格や建設コスト、運用コストが高騰していることから、新規の大規模データセンターを建設・運用するには莫大なコストが必要になります。

一方、地方都市では比較的低コストで土地を確保できるため、建設・運用コストを抑えられます。ただし、ネットワーク接続拠点から距離がある場合には、通信インフラの整備に追加コストがかかるケースもあります。
新規建設の難しさ
都市部では、土地価格の高騰やスペース不足に加え、環境負荷や景観への懸念から建設反対運動が起きやすく、新規データセンターの建設はハードルが高い状況です。
地方都市は土地価格の安さや広大なスペースを確保しやすい点から大規模なデータセンターを建設しやすいといった利点があります。しかし、地方都市でも住宅地に近い場所では、騒音や地域景観への影響を理由に地域住民から建設反対運動が起こるケースも増えています。
このように、都市部・地方都市ともに、データセンターの新規建設には物理的制約と社会的合意形成という二重のハードルが存在します。
地方分散型データセンター選定のポイント
地方分散型のデータセンターを選定する際は、いくつか確認しておくべき点があります。
ここでは、地方分散型データセンター選定の3つのポイントを解説します。
災害リスクの低さ
地方分散型データセンターを利用する目的の1つは、災害発生時のリスク分散です。地方都市のデータセンターを選定する際は、地震・水害・台風など自然災害リスクの低さがポイントになります。
選定時には、自治体のハザードマップや地震動予測地図を活用し、活断層や浸水区域との位置関係を確認しましょう。さらに、電力供給や通信回線が災害時にどの程度維持されるか、冗長性の有無を確認することも重要です。
また、データセンターの耐震構造や災害時のバックアップ体制についても確認しましょう。
運用体制
地方型データセンターに限らず、運用体制やサービス内容も選定のポイントになります。24時間365日の監視体制や障害発生時の対応力、リモートメンテナンスサービスの有無など、運用体制や提供サービスが「自社が求める水準」に達しているかを確認しましょう。
また、入退室管理や監視カメラなどの物理的セキュリティ、サイバー攻撃対策などのシステム的セキュリティなど、セキュリティ体制が十分であるかも選定のポイントになります。
環境への配慮
カーボンニュートラルの実現が求められていることから、環境への配慮も重要なポイントです。特に、地方型データセンターは再生可能エネルギーを利用しやすいといった特長があるため、環境配慮のためにどのような取り組みをしているのかを確認しましょう。
環境への負荷を最小限に抑える設計や運用がされるデータセンターは「グリーンデータセンター」とよばれます。
グリーンデータセンターの詳細については、第07回のコラムをご参照ください。
「地方分散型データセンター」のまとめ
地方分散型データセンターは、都市型データセンターの課題である土地確保、高コスト、災害リスク集中などの課題を解決するために有効です。
選定にあたっては災害リスク、環境への配慮、運用体制などを総合的に評価することが重要です。
また、都市型と地方型の両方のデータセンターを組み合わせ、それぞれの利点を活かすハイブリッド型の活用例も増えています。
たとえば、本コラムを掲載している鈴与シンワートでは、「東京第一」「東京第二」センターは都市型として利便性、耐震性、設備の信頼性を重視し、大阪、北陸、九州、沖縄などの拠点は地方型として地域分散によるリスク低減、BCP対策を可能にします。
今後はデータセンター選定に、運用体制やサービス内容に加え、データセンターの立地や複数拠点での運用の可否も視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか。
鈴与シンワートが提供している「S-Port データセンターサービス」では、専門チームによるサーバやネットワーク、ストレージなどの初期設定や構築作業、24時間365日の監視や障害対応など、幅広いサービスを提供しています。
貴社の要望や予算に応じたサービスの提案をします。ぜひお気軽にご相談ください。