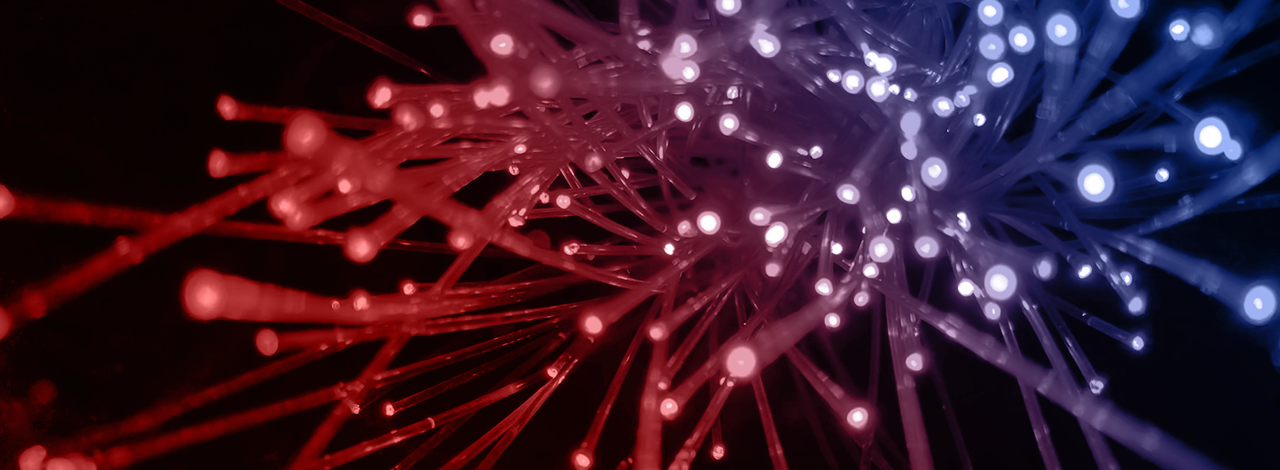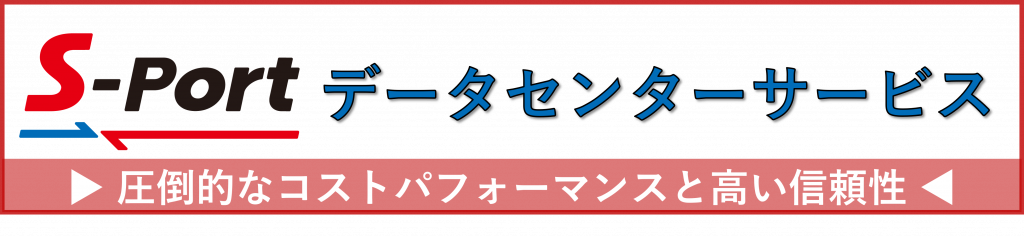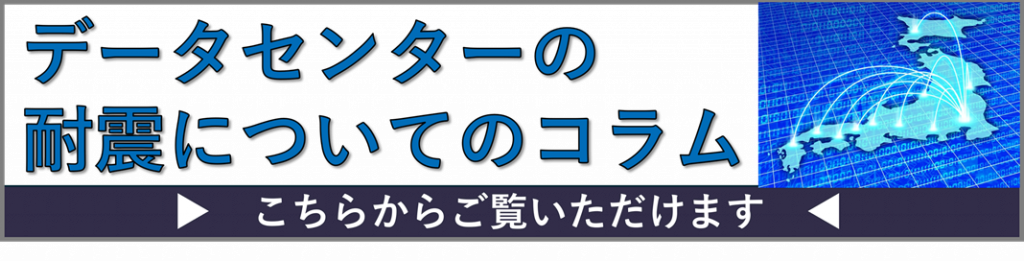サーバルームとは ~必要な設備や注意点を解説〜 第08回 25年01月 / 最終更新:2025.01.28
目次
サーバルームは、サーバなどの機器を適切に運用するための専用スペース(オンプレミス)を指すことが一般的です。サーバルームは機器を安定的に稼働させるために、専用の設備や環境を整備する必要があります。
今回は、サーバルームを設置するメリットや必要な設備の紹介と、サーバルームを設置する際の注意点や「これからのサーバ運用」に関する検討ポイントを解説します。
サーバルームのメリット
通常の執務スペースとは別の専用空間にサーバルームを用意することで、機器の安定的な稼働やセキュリティの確保など、さまざまなメリットを得ることができます。サーバルーム設置のメリットを具体的に解説します。
機器の安定稼働
サーバやネットワーク機器は精密機械であり、温度変化や埃などの外的要因によって、故障やシステムダウンなどのトラブルが発生することがあります。従いまして、適切な空調管理や埃対策などをすることで、外的要因によるリスクを最小限に抑えることができます。
さらに、定期的な点検やシステム監視を導入することで機器の異常を検知でき、可用性を高めることができます。
セキュリティの確保
執務スペースとサーバルームを分けることは、セキュリティが確保できるといったメリットがあります。
専用空間を設けることで入室制限や入退室管理ができるため、外部からの侵入や、内部不正といったリスクを軽減することができます。
サーバルームに必要な設備
サーバやネットワーク機器を安全に運用するために、サーバルームにはいくつかの専用設備が必要です。サーバルームに求められる代表的な設備を紹介します
空調設備
サーバ機器は動作中に大量の熱を発生させます。機器を安定的に稼働させるためには、発生した熱を効率よく排出し、温度を一定に保つことが不可欠です。サーバルームでは専用の空調設備が設置されることが多く、冷却効率を最大化するために風量や空気の流れを調整するシステムが採用されています。また、機器の排熱方向を揃えることで、熱い空気と冷たい空気を分けて冷却効率を上げる工夫がされています。熱い空気の通り道を「ホットアイル」、冷たい空気の通り道を「コールドアイル」と呼びます。
さらに、温度管理だけでなく湿度管理も重要です。湿度が高すぎると機器内部が結露し、低すぎると静電気によるダメージが生じることがあります。これらを防ぐため、空調設備には湿度センサーや湿度調節機能が搭載されています。
電源設備
予期せずにサーバなどの機器の電源が切断された場合、データ破損や物理故障などのトラブルが起きることがあります。そのため、UPS(無停電電源装置)や冗長化された電源システムが必要です。
停電時にはUPSが瞬時に作動し、サーバなどの機器の電源切断を防ぎます。UPSが稼働している間に安全にシャットダウンし、バックアップ電源へ切り替える、などの対応をすることで重要なデータが失われたり、機器が物理故障したりするリスクを回避できます。
物理的なセキュリティ対策
サーバルームの物理的なセキュリティ対策は、外部からの侵入を防ぐために重要です。サーバラックの施錠管理だけでなく、監視カメラや入退室管理システムを導入することで、部外者が重要なデータに不正アクセスするリスクを抑えることができます。
さらに、生体認証やICカード認証といった認証システムを導入し、入退室の記録を残すことで、より厳密にセキュリティ対策ができます。これらの対策は、外部からの侵入だけではなく内部不正にも効果があり、インシデント発生時の証跡にもなります。
サーバルーム設置の注意点
サーバルームは機器の安定稼働に不可欠ですが、いくつかの課題や注意点があります。
サーバルームの設置や運用に関する注意点を解説します。
コストがかかる
サーバルームを新設する場合には多額の投資が必要です。空調や電源設備、セキュリティシステムの導入に加え、各種装置の設置工事費用がかかります。また、運用にも電気代やメンテナンス費用、人件費などの継続的なコストがかかります。
物理的なスペースが必要
サーバルームは空調管理やセキュリティなどを考慮して、執務スペースとは別に専用空間を設けることが推奨されます。そのため、オフィスの環境によっては、サーバやネットワーク機器を設置するスペースや部屋の確保が物理的に難しいケースがあります。
十分な災害対策が困難
サーバルームは企業や組織の内部に設置されるため、耐震性や防災性はその建物に依存することになります。そのため、建物自体の耐震性や防災性が不十分な場合、サーバ機器を災害から守ることは困難です。特に地震の多い地域では、耐震ラックや防災システムの導入が推奨されますが、入居している建物に依存しているため、導入が難しい場合もあります。
これからのサーバ運用
以前はオンプレミスでのサーバ運用が主流でしたが、現在はサーバ運用に求められるニーズも多様化しています。「これからのサーバ運用」についての検討ポイントを解説します。
外部データセンターの利用
サーバは、機密データの保管や、重要なシステムを稼働させる必要があるため、高い可用性やセキュリティが求められます。
データセンターは耐震設計や防災対策が徹底されており、自然災害に対して強い構造を持っています。また、複数の地域に分散された拠点を持つデータセンターでは、障害時にも他の拠点がバックアップとして機能するため、DRやBCPの対策にもなります。
多くのデータセンターが最新のセキュリティを取り入れており、24時間体制で監視されています。そのため、自組織でデータセンターを所有していない場合は、外部データセンター活用の検討をおすすめします。
クラウドサービスの利用
現在はクラウドサービスの利用が普及しており、オンプレミスのサーバをクラウドサービスへ移行するケースも増えています。クラウドサービスは一般的に利用した分だけ料金が発生する従量課金制が採用されています。初期費用を抑えることや、運用コストなどが不要になることから、コスト削減につながることがあります。
また、オンプレミスとクラウドサービスを併用するハイブリッド環境の構築が適しいているケースもあります。必要に応じてオンプレミスとクラウドサービスを使い分けることで、バランスの良い運用が可能です。
環境への配慮
近年、ICTの普及により、サーバやネットワーク機器の電力消費問題が重要な課題となっています。そのため、再生可能エネルギーを利用した電力供給や、高効率な空調設備の導入など、環境に配慮したデータセンターの活用が注目されています。
「これからのサーバ管理」では、環境に配慮したデータセンターを積極的に活用するなど、サステナブルな社会の実現に向けた取り組みをすることも重要です。
サーバルームのまとめ
サーバルームは、機器を安定的に稼働させるためにさまざまな設備の導入や工夫がされています。また、セキュリティを担保できるといったメリットもあります。
しかし、コストやスペースの問題、災害対策の難しさなど、いくつかの課題もあります。そのため、「これからのサーバ管理」では、外部データセンターやクラウドサービスの活用を含めた柔軟な管理が求められます。
サーバなどすべてのIT機器をサーバルームで運用している場合は、コスト削減やDR対策、BCP対策などを考慮して、外部データセンターやクラウドサービスの利用、ハイブリッド環境の構築などを検討してみてはいかがでしょうか。
鈴与シンワートは東京、大阪・北陸・九州・沖縄にデータセンターを展開し、ハウジングサービスやクラウドサービスを提供しています。
データセンターやクラウドサービスの利用を検討されている方は、 ぜひお気軽にご相談ください。